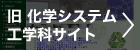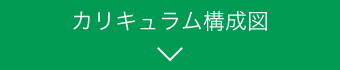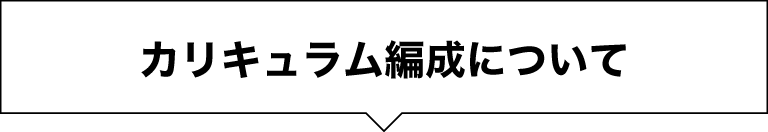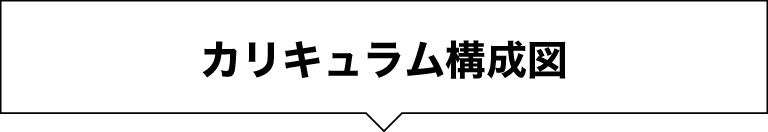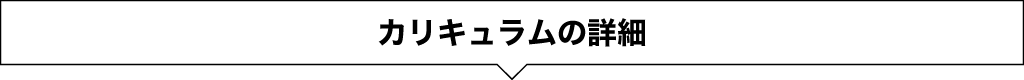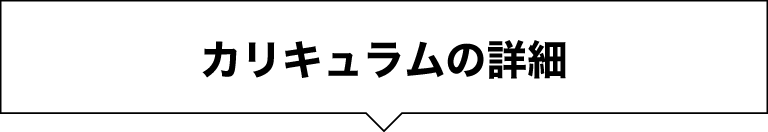総合工学概論
工学は真理を探求し,有用な科学・技術を研究・開発するとともに,その成果の社会への還元を目指す学問分野であり,「総合工学」とは工学における横断分野である。これまでの日本・世界・新潟県における工業への工学の貢献ならびに工学の諸分野における考え方をテーマとして学ぶことによって「総合工学の基本的な考え方」を理解していく。なお本科目は,機械設計や生産技術,品質マネジメント,知的財産管理の実務経験を有する教員が,それを活かして生産工学,工業経営の基礎と企業における実際の応用について授業を行います。また,企業においてアナログおよびディジタル製品の開発経験を有する教員が,それを活かして電子情報通信工学の基礎と応用について授業を行います。
総合技術科学演習
はじめに力学,情報電子,化学材料,建築,融合領域の5分野を紹介し,次にそれぞれの分野における「つくる&はかる」をテーマにした演習を実施し,基礎的な知識と考え方を身につけていきます。 また,実務経験のある教員による製図の基礎に関する解説を行います。
技術者の心がまえ
研究者及び技術者として望ましいな行動をデザインするためには,様々な分野において「適切な判断」を下せる能力が求められる。本科目では,研究者及び技術者が判断,あるいは自分の行動を律しなければならない分野のうち,「研究倫理」「技術者倫理」「安全」「情報倫理」「ビジネス倫理」などの分野を取り上げ,各場面特有の課題及び考え方のポイントを理論および事例を交えながら学びます。
知的財産概論
モノとして実物のあるパソコン、自動車、家屋などは通常、所有者が存在し、所有者はそれらを使用したり譲渡する権利を持ちます。一方、新しい素材の作り方、新しい素材による新機能の発現方法、便利な装置の新しい構成や構造や、コンピュータプログラムによって実現される新奇な情報処理技術、特定の工業製品が備える優美なデザインといった、ヒトの知的活動によって生み出された創作や発明には実物は存在しないものの、これら成果に対する創作者の権利は保護されて然るべきです。後者を総括して知的財産権と呼びます(産業上利用可能な知的財産権を特に産業財産権と呼ぶ)。本科目では、エンジニアが当然備えておくべき知的財産全般の考え方ならびに関連制度を包括的に理解し、産業や研究活動によって生じるであろう権利の発生要件や、第三者からの権利侵害への対抗あるいは自らの活動が第三者の権利侵害をひきおこさないための基礎知識を学びます。
情報セキュリティ概論
コンピュータシステムは、社会や企業活動において重要な情報を大量に扱うものとなっています。これら情報資産には、機密情報や顧客の個人情報等、厳密な取扱いを求められるものが少なくありません。しかし、ウィルス感染、データの盗難、不正アクセス等による情報漏洩事件が後を絶たちません。個人や企業を問わず、インターネットを利用した活動も盛んとなり、Webサイトを通じた情報の公開や電子メールの使用は日常のことであり、サーバ侵入やWebページ改ざんを試みる悪意の者の標的となっています。このような脅威に対して、個人や組織の一員としてパソコン(情報端末機器)を利用する立場からどのように対処したら良いのか(セキュリティ対策)を解説します。
国際工学概論
工学の各分野について,グローバルな視点に加え,地域社会の活性化の観点から基礎的な専門知識を修得することを目的に、工学の様々な分野の専門家が英語で概説します。また,その修得した知識を基に,工学が世界においてどのように役立っているかディスカッションをします。
基礎数理AI
工学をはじめ、データを分析する学問分野において、数学の素養は欠かせません。本講義では、理工学の諸分野を学ぶ上で必須の微積分学について扱います。特に1変数函数の微積分学を学びます。
基礎数理AII
この科目で学習する多変数関数に対する微分積分学は,ベクトル解析,複素関数論など数学の分野を習得する上で重要な基礎となり,また現実的な理工学の諸問題の理解・解法のための必要な道具です。この科目では多変数関数の微分積分学の基礎理論を学びます。
基礎数理B
データの分析や、自然現象を記述する微分方程式の解法など、理工学の諸問題にはしばしば多変数の方程式が現れます。本講義ではそのうち多変数連立1次方程式を解く上で極めて有用な線形代数学について学びます。
物理学基礎BI
物理学の基礎である古典力学(ニュートン力学)を学びます。この科目では、扱う対象を質点の力学に限定して、速度、加速度、力、運動量、エネルギーなど、物理学の基礎的概念や、物体の運動を記述する手法を学びます。
物理学基礎BII
物理学基礎BIで学んだ質点の力学をさらに発展させ,多数の質点からなる系(質点系)や広がりをもった物体(剛体)の運動を学びます。さらに,日常生活で馴染み深い振動や波動現象の基本的性質も学びます。その中で,これらの運動を記述するために不可欠な数学を理解し,その取り扱いに習熟することを目指します。なお,本科目は実務経験のある教員によって行われます。
工学リテラシー入門(化学材料分野)
創造性を発揮するためには,知識を組み合わせることが必要です。この科目では,学生を少人数の班に編制して,実験を通して知識と経験を統合して解を創造するためのチームプロジェクトを行います。応用化学系テーマ、化学工学系テーマ、材料物性系テーマ、材料開発系テーマの中から一つのテーマについて学生が自ら実験計画を立てて実験を行い,結果を自分で検証・考察します。さらに,その考察に基づいて実験計画を見直して再度実験を行い,結果や考察の検証を行うプロセスを通して,知識や経験を組み合わせて工学的解を導く方法を学びます。「知識の暗記だけで使える”つもり”になっている」学習法では、学力は伸びない。”つもり学習”の悪癖に気づき、改める実践的な教育方法として「失敗しつつもそれを強い意欲で乗り越えて成功する体験を組み込んだ」教育プログラムを行います。高校までの知識暗記型学習から,工学的解を得るための知識統合型学習への橋渡しをします。
エンジニアのためのデータサイエンス入門
エンジニアの観点からデータサイエンスの基礎を学ぶことを目的とし、データサイエンスが必要とされる背景やデータサイエンスの仕組みを学習、理解します。
生活を支える化学技術
金属やプラスチック,医療品,化粧品,衣料,塗料など私たちの身の回りにあるものは,天然物以外すべて化学反応を利用して作られています。でも,化学反応だけでは材料や製品を作ることはできません。化学反応で生成した目的物質を不純物(未反応原料,副生成物など)からより分けて,必要な純度に精製してはじめて素材になります。素材を組み合わせて材料を作り,材料を組み合わせて製品を作ります。
化学工場では化学反応を利用して原料から化学物質を生産しますが,原料やエネルギーを有効に使い,有害な汚染物質を環境に排出しないようにして生活に役立つ製品を作るための学問が化学工学です。つまり,化学工学は,化学を通して環境に優しく生活を豊かにするための学問です。化学工学の「環境に優しく省エネ・省資源で化学的にもの作りをする」という考え方は料理や掃除などの家事にもあてはまります。例えば,おいしい料理を作るためには良い食材と良いレシピが必要ですが,食材を有効に利用してゴミを減らし,消費エネルギーも減らすことが重要です。化学工学は料理を作る上のレシピに相当します。この科目では,生活の中で私たちが行っている技術や現象を通して,化学工学の考え方を解説します。
最先端技術を支える化学Ⅰ
化学はわれわれの生活や産業に密接に係わっている重要な学問です。本講義では,身の回りの物質や最先端の人工(合成)材料への化学の役割,地球環境問題や生活との化学の係わりあいについて解説します。
化学システム応用数理
化学システム工学プログラムでは実験で得られた結果を生産プロセスに適用するため、数学的な手法でモデル化し、スケールアップに対応する必要です。化学システム工学プログラムの学生は、得られた実験結を整理、解析、モデル化し、それらのデータの元で、装置の設計をする能力が求められます。本講義ではこれらに必要な基礎数学の知識を学びます。化学システム工学プログラム学生として必要な数学的基礎知識、解析能力を身に付けるため、微分方程式、偏微分方程式、連立微分方程式などを工学の観点から学びます。数学の基礎理論を学ぶとともに、数学の基礎知識を確認し、実験結果のモデル化、データ解析、装置設計などの能力を培います。
応用数理B
微分方程式は物体の運動を記述するために考えだされましたが,その適用範囲は力学だけでなく,電磁気学を含む物理分野,さらには多くの自然科学分野や,社会現象を記述するためにも用いられています。この科目では微分方程式の解法や基礎理論について学びます。
基礎物理工学
電磁気学は理工学の土台の中心の1つであり、原子・分子や原子核の内部といった超極微の世界や万有引力などの力を除けば、自然界の物質の性質や変化・反応を司る力は電磁気力が起源である。つまり化学が主なテーマとする原子・分子レベルの諸現象も、(量子力学の効果を除けば)すべて電気磁気相互作用のみから説明されるとさえ言える。多くの物理学者が関わり構築してきた電気的(磁気的)相互作用の基礎を修得しながら、「当たり前のことを疑う」という物理学の精神を学ぶ。公式を記憶し数値を代入し計算することが物理学ではない、ということを実感する。