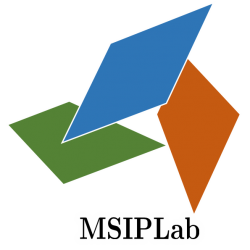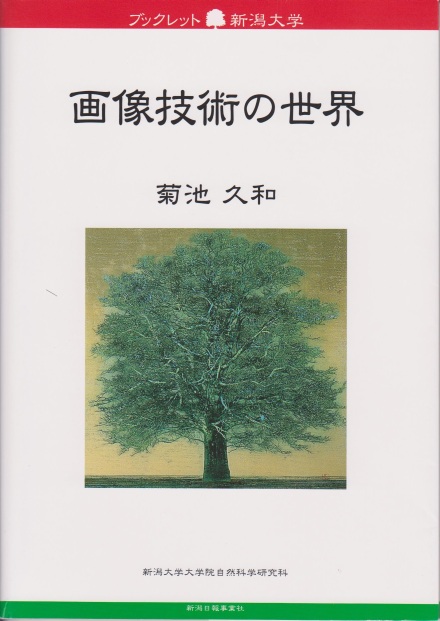ブックレット新潟大学 66
画像技術の世界
菊池久和 著, 新潟日報事業社 発行
ISBN 978-4-86132-605-9 http://www.nnj-book.jp/
- カラーでないと分からない図は 図14~18, 36, 38, 39です。
- カラーでないと分かりにくい図は 図5, 6, 7, 13, 21, 23, 28, 32です。
 図1 テレビの解像度
図1 テレビの解像度
 図2 解像度のちがい。解像度が2倍になると滑らかでくっきりした輪郭が再現される
図2 解像度のちがい。解像度が2倍になると滑らかでくっきりした輪郭が再現される

 図3 階調数が256とおりの濃淡画像(上)。これの誤差拡散ハーフトーン(下)。階調は0と255だけで、階調数は2とおり。
図3 階調数が256とおりの濃淡画像(上)。これの誤差拡散ハーフトーン(下)。階調は0と255だけで、階調数は2とおり。
 図4 誤差拡散。量子化誤差を周辺に分配する
図4 誤差拡散。量子化誤差を周辺に分配する
第1章
 図5 17ドットディザースクリーン
図5 17ドットディザースクリーン
 図6 ディザーハーフトーンの例。左は原画、右がハーフトーン。 ドット凝集ハーフトーンをよく見るには画像をクリックして拡大してください
図6 ディザーハーフトーンの例。左は原画、右がハーフトーン。 ドット凝集ハーフトーンをよく見るには画像をクリックして拡大してください
 図7 ハーフトーンの拡大図。RGBに対応するスクリーンが別々の角度 (76, 14, 0度)で傾斜していることが分かる
図7 ハーフトーンの拡大図。RGBに対応するスクリーンが別々の角度 (76, 14, 0度)で傾斜していることが分かる
 図8 色度図とsRGB色空間の色域。小3角形は現在主流のBT.709色域。大3角形は4K/8KテレビのBT.2020色域。Wは白点
図8 色度図とsRGB色空間の色域。小3角形は現在主流のBT.709色域。大3角形は4K/8KテレビのBT.2020色域。Wは白点
 図9 跳び越し走査映像の1コマ(左)を可逆デインタレース処理で順次走査映像の1コマ(右)に変換
図9 跳び越し走査映像の1コマ(左)を可逆デインタレース処理で順次走査映像の1コマ(右)に変換
第2章

 図10 レティネクス処理。原画像(上)と処理結果(下)
図10 レティネクス処理。原画像(上)と処理結果(下)
 図11 3つのスケール(左から小、中、大)で推定された周囲光分布(上段)と反射率分布(下段)
図11 3つのスケール(左から小、中、大)で推定された周囲光分布(上段)と反射率分布(下段)
第3章
 図12 ベイヤー型カラーフィルタ配列
図12 ベイヤー型カラーフィルタ配列

 図13 原画シーン(上段)とモザイク撮像画(下段)
図13 原画シーン(上段)とモザイク撮像画(下段)
 図14 カラーデモザイキングの比較、その1。左から適応色補間法、中央値法、色相平滑化法
図14 カラーデモザイキングの比較、その1。左から適応色補間法、中央値法、色相平滑化法
 図15 カラーデモザイキングの比較、その2。左が適応色補間法、右が色相平滑化法
図15 カラーデモザイキングの比較、その2。左が適応色補間法、右が色相平滑化法
 図16 カラーデモザイキングの比較、その3。左から 原画像、適応色補間法、原色整合軟判定法、色相平滑化法
図16 カラーデモザイキングの比較、その3。左から 原画像、適応色補間法、原色整合軟判定法、色相平滑化法
第4章

 図17 黒体放射の色度軌跡(上)と無彩色の色づき(下)。 150ミレド付近が色温度6500度の昼の太陽光に対応し、無彩色が灰色に見える
図17 黒体放射の色度軌跡(上)と無彩色の色づき(下)。 150ミレド付近が色温度6500度の昼の太陽光に対応し、無彩色が灰色に見える


 図18 色温度による色調変化。色温度は左上が2500度、右上が5500度、左下が9300度
図18 色温度による色調変化。色温度は左上が2500度、右上が5500度、左下が9300度
 図19 低露光、中露光、高露光で撮影した画像。中央の窓から見える外の物体にも注目しよう。
図19 低露光、中露光、高露光で撮影した画像。中央の窓から見える外の物体にも注目しよう。
 図20 いいとこ取り。左上、中央、右下が各露光撮影における適正露光部分
図20 いいとこ取り。左上、中央、右下が各露光撮影における適正露光部分
 図21 露光合成画像
図21 露光合成画像
第5章
 図22 確率の併合と、分岐のラベルづけによるハフマン符号化
図22 確率の併合と、分岐のラベルづけによるハフマン符号化
 図23 画像(左上)とそのDCT(右上)。DCTの左上領域4% だけ(右下)を逆DCTすると近似画像(左下)が得られる
図23 画像(左上)とそのDCT(右上)。DCTの左上領域4% だけ(右下)を逆DCTすると近似画像(左下)が得られる
 図24 3つのDCT成分(上の3段)とその加算によって作られる波形(下段)
図24 3つのDCT成分(上の3段)とその加算によって作られる波形(下段)
 図25 DCTブロックにおけるジグザグ走査
図25 DCTブロックにおけるジグザグ走査
 図26 原画像(左)の75%のDCTデータを棄却して得られる画像(右)。
図26 原画像(左)の75%のDCTデータを棄却して得られる画像(右)。
第6章
 図28 原画像(左欄)の水平垂直2段ウェーブレット変換の結果(右欄)
図28 原画像(左欄)の水平垂直2段ウェーブレット変換の結果(右欄)
 図29 GOPにおける画面符号化の様子。 I画面は単独で符号化される。 P画面はI画面から予測される。 B画面はI画面とP画面から順逆両向きに予測される
図29 GOPにおける画面符号化の様子。 I画面は単独で符号化される。 P画面はI画面から予測される。 B画面はI画面とP画面から順逆両向きに予測される
 図30 ビデオ符号化のブロック図
図30 ビデオ符号化のブロック図
 図31 HEVCにおける符号化ブロックの木と符号化ブロック
図31 HEVCにおける符号化ブロックの木と符号化ブロック
第7章
 図32 SBCによる関心領域 (ROI, region of interest) の復号例
図32 SBCによる関心領域 (ROI, region of interest) の復号例
 図33 SBCとJPEG2000における関心領域復号の比較。(左)SBCは 任意形状をくっきりと復号できるが、(右)JPEG2000ではぼける。
図33 SBCとJPEG2000における関心領域復号の比較。(左)SBCは 任意形状をくっきりと復号できるが、(右)JPEG2000ではぼける。
第8章
 図35 大津の2値化による領域分割
図35 大津の2値化による領域分割
 図36 色相による肌色領域の抽出
図36 色相による肌色領域の抽出

 図37 グラフカットによる釘脚輪郭の抽出
図37 グラフカットによる釘脚輪郭の抽出
 図38 色彩類似度 0.97
図38 色彩類似度 0.97
 図39 色彩類似度 0.85
図39 色彩類似度 0.85
付録
- 本書では千倍ずつ異なる数値を表わす補助単位が何度も登場しますので、表に記します。
- 補助単位とは「1kmは1000m」というときのキロがそれです。
- たとえば光速は毎秒30万kmです。1ナノ秒では0.3m、1ピコ秒では0.3mm進みます。こう言うと光も何だかおそいと感じませんか。
- また100年は3ギガ秒だというと、人生がとても短い印象になります。