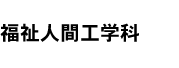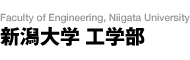 |
|
|||
| トップ > 学科案内 > 福祉人間工学科 > 教育プログラム・カリキュラム | ||||
|
福祉人間工学科の教育プログラムは、エンジニアとしての電気電子工学や情報科学の知識を備え、なおかつ、福祉の文化にもとづいた、使う人の立場に立った機械システムの設計思想を持った人材を育成し、21世紀の新しい学問・文化をリードする国際的視野に立つエンジニアを養成するための教育プログラムです。 科目は専門基礎科目、専門科目、および実験・実習・演習科目の3つに大別することができます。専門基礎科目は工学の基礎となる数学・物理を学びます。専門科目は電気電子工学、情報工学、機械工学を学ぶ科目と,福祉工学や医用工学を学ぶ科目とがあります。専門科目は基礎科目から応用科目を段階的に学ぶことができるようになっており、特に基礎科目については演習を併用して確実に理解できるようになっています。また、工学の基礎となる科目、および医用・福祉工学科目の基礎的な内容に関する実験・実習を1年前期から3年後期までの各期に開講し、講義の内容をより深く理解できると共に、学んだ知識を実践で活用できる能力を習得できるように工夫されています。 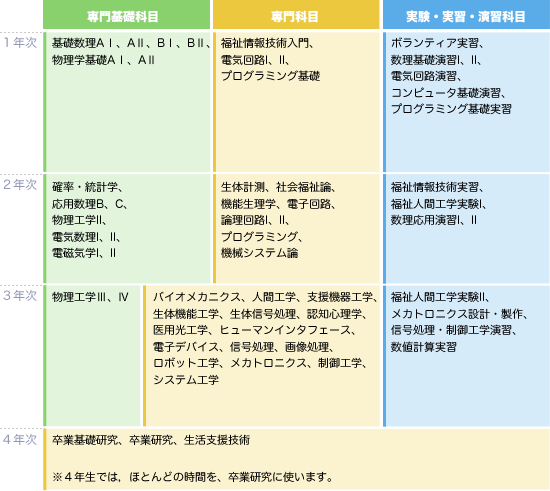 ■1年次 1年次では専門科目を学ぶ上で最低限必要となる、数学・物理を中心に学びます。また、電気回路やプログラミングなど電気電子情報系の基礎科目を学びます。ボランティア実習は入学して初めて履修する福祉系科目で、社会福祉の意義や必要性を学びます。 ■2年次 2年次でも専門基礎科目を中心に学びますが、医用・福祉工学の基礎となる、生体計測や論理回路などの専門科目も学びます。福祉情報技術実習では現場で使われている福祉技術を学びます。 ■3年次 3年次では専門科目を中心に学び、高度な専門知識を習得します。ヒトの感覚や感性、身体能力を人間工学と医学の両側面から学ぶことで、使う人の立場に立った機械システムの設計思想を習得します。また、情報・電子工学分野と機械工学分野の接点である、メカトロニクス、ロボット工学も学ぶことができます。基礎的な専門科目については演習を行い、確実な知識やスキルの習得を目指します。 ■4年次 4年次では卒業研究テーマを通して、3年次までに培った専門知識より深く理解するとともに、問題を発見、解決する能力を養い、福祉リテラシーをもつエンジニアとしての基礎を築きます。 |
 |
|