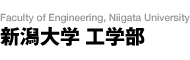私たちは日常生活の中で無意識のうちに視覚から多くの情報を取得しています。例えば外を歩く私たちの視界には、空を飛ぶ鳥、道を歩く犬、公園で子供が投げたボール、道路を走る車など多くの視覚情報が存在しています。これらの視覚情報から、私たちは身の回りに存在する物体と自己との位置関係やその変化を把握し、より適切な行動を取ることで日常を送っています。このように、「見る」ことは、私たちにとって物体の存在とその運動とを認識することや、観察者自身の外界における位置・方向・運動を認識することであり、また、そうした視覚情報をもとに対象物へ手を伸ばしたり、姿勢や進行方向を制御したりするなど行動制御を行うことであると言えます。
近年の映像技術の向上に伴い、我々は日常生活の様々な場面で臨場感のある映像コンテンツを見ることができるだけでなく、自ら映像を制作し配信することが容易にできるようになりました。その一方で、映像による負の生体影響である映像酔いや眼精疲労に関する報告を目にする機会が増えており、いわゆる技術優先でなく人間工学的側面をも踏まえて、映像利用の負の側面を十分に把握し、また映像の効果的活用に向けた2つの観点からの取り組みが必要です。
私の専門分野は、人の知覚反応と刺激の物理特性を定量的に結び付けることで人の感覚・知覚メカニズムを科学的に明らかにする心理物理学、人の視知覚の特性を工学的技術に応用する視覚工学、人の生体情報を数値化して取り扱う生体計測学です。これらを通して得られる知識や技術を用いて人の生活の安全や健康のために役立つ機器の開発や支援技術を構築することを目指しています。
“支援方法の一つとして、人に対する映像による負の生体影響を軽減するものが挙げられます。一人称視点のダイナミックな動きを伴う映像や手振れ映像を視聴することで、頭痛、めまいや吐き気を伴う映像酔いと呼ばれる症状を発症することがあります。これに対しては、映像に含まれる運動成分や周波数、振幅などを考慮した上で、映像視聴中の人の心電図や脈波といった生体信号、さらに人の映像酔いに対する主観的な評価を組み合わせることで映像酔いの予測を行う技術が有効になると考えています。
また、様々な障がいからの自立を支援する時代において、支援を必要とする人のニーズに合わせた、もしくは、各々が個人の特性に合わせてセルフカスタマイズできるような福祉工学的応用技術が求められています。そのような状況においても、映像の効果的な活用を通して障がいを持つ方々が安心して利用できるリハビリテーション手法の確立や、支援技術への理解を深めるための教育活動を進めていきたいと考えています。

多くの生物は、移動によって情報や生存環境、食料を獲得し、環境変化へ適応することで進化を遂げてきました。ヒトにとっては行動範囲を拡げることや、移動手段を得ることは、好奇心を刺激し、行動や生活の意欲を増してくれることもあります。すなわち、「移動すること」は、私たちにとっての根源的な活動要素ともいえます。
少子高齢化社会を迎え、また様々な障がいからの自立を支援する現代において、多くの人の移動の障害を減らすバリアフリーという考え方が浸透してきています。段差の少ない通路やエレベータやエスカレータの整備といった、社会の基盤整備が進められる一方で、怪我や疲労によって生活行動や移動に不便が生じた場合には、個人レベルで移動の支援が必要となってくるでしょう。
私の専門分野は、人やモノの動きを数値化して取り扱う計測工学、機械や現象をあやつる制御工学、機械的な仕組みを設計する機構学です。これらの工学技術を、電子回路技術やコンピュータソフトウエアで統合したものはメカトロニクスと呼ばれ、社会のシステムや福祉技術などと多くの接点があります。そこで、この技術を個人レベルの移動支援に応用し、機器開発や支援技術を構築することを目指しています。
その支援方法の一つは、ヒトの動きをサポートするものです。椅子から立ち上がり、段差や階段を上り下りするなどの動作は、筋力の低下や怪我によって力を出せない場合には困難なものとなります。これらに対しては、モータの回転力や空気の圧力などの他の力の助けを得る技術が有効となります。また、屋外では、自転車や自動車など、より大きなエネルギーや速度を操る移動手段が増えるため、周囲のヒトや車との接触・衝突を避けて安全を確保する高度な判断と操作が要求されます。疲れていたり眠くなっていたりして判断や操作が難しい状況では、カメラやレーダーから得られる情報でヒトの知覚を、また操作行動の解析・評価結果からヒトの操作を、それぞれ支援する技術が応用できます。
近い将来、多くの移動手段は、知能化・自動化された機械やロボットが担うかもしれません。場合によっては、ヒトが移動から得てきた、好奇心を満たす経験や行動したいという意欲が低下してしまうかもしれません。そのような状況においても、安全な移動を支援する技術とそれを使うヒトとの関係がよりよいものとなるよう、ヒトの移動を中心とした支援技術の研究や、支援技術への理解を深めるための教育活動を進めていきたいと考えています。

受動歩行理論を用いた歩行おもちゃの製作教室

ドライバ行動計測のためのハンドル内蔵型圧力センサ