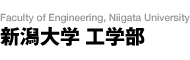 |
|
|||
| トップ > 学部案内 > 教育・研究活動 > 教育改善への取り組み | ||||
|

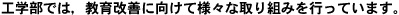
学生が講義を受ける際には、
・CAP(キャップ)制
を導入しています。・GPA
CAP制とは、1学期(セメスター)に履修する科目を登録する際、その合計単位数に上限を定める制度です。頭に帽子をかぶせて、上限を設けているという意味で使われています。この趣旨は、むやみに科目数だけ多く登録しても勉強が追いつかずに単位が取得できない ようなことが起こらないように、そして個々の科目の消化不良を防ぐためです。
GPAはGrade Point Average の略で、米国において一般的に行われている学生の成績評価方法の一種です。履修した個々の授業科目の評価に応じてGP (Grade Point)を与え、GPAは、獲得したポイントの合計を履修した総単位数で除した1単位あたりの成績の平均値です。GPA 制度の狙いは、卒業時の能力に照準を合わせ、学生の学力の到達水準を明確にして、「学ぶ量ではなく、学ぶ質を問う」ことにあります。そして、累積GPAは席次評価などに使われます。 授業評価アンケート
各学期、科目毎のアンケートを行い、学生の要望も取り入れ教育改善に役立てています。
早期卒業・大学院への飛び入学
累積GPAが3.7以上で、各学科が実施する最終審査に合格した場合、3年間で早期卒業できる制度があります。
また、大学院への飛び入学制度があります。
卒業研究(設計)優秀賞
教育改革には、教員側の努力と意識改革が必要であると同時に、学生側の意識改革、すなわち、“教わる”形態から“自ら学ぶ”形態への変革が必要です。そのきっかけを作るべく、1999年度から“卒業研究(設計)優秀賞の表彰制度”を導入しました。一生懸命がんばった学生に優秀賞を授与することで、学生みなさんの励みになればとの願いからです。
各学科とも4年次学生の4%を目途に優秀な学生を推薦し、表彰は卒業祝賀会の席上で行っています。 教育賞
教育に関して顕著な実績のあった教員にその功績をたたえ、表彰を行っています。
「創造プロジェクトI・II」
工学部は有形であれ無形であれ「ものづくり」に関した技術開発や学術研究を行うところですが,この科目では,「ものづくり」の楽しさや達成感を味わうことができます。
この科目の特色は,工学部の学生であれば誰でも聴講することができ,受講を希望する学生がチームを組んで、あるいは、単独で自分自身のテーマを持参して参画すること、学科・学年の枠を超えた学生のプロジェクトチーム結成を目指していることです。
 自主的に進めるというのが基本で、且つものづくりのための時間が結構必要ということから、両科目ともに課外時間や夏休みなどを有効利用することになります。
各チームは月1回定例の進捗状況報告会に合わせてプロジェクトを進めて行きます。プロジェクトの作品は長崎大学、富山大学、新潟大学の各大学で行われる「学生ものづくり・アイディア展」に出展することになっており、それを目指してプロジェクトを進めることになります。
自主的に進めるというのが基本で、且つものづくりのための時間が結構必要ということから、両科目ともに課外時間や夏休みなどを有効利用することになります。
各チームは月1回定例の進捗状況報告会に合わせてプロジェクトを進めて行きます。プロジェクトの作品は長崎大学、富山大学、新潟大学の各大学で行われる「学生ものづくり・アイディア展」に出展することになっており、それを目指してプロジェクトを進めることになります。「創造プロジェクトI」では、課題設定と計画立案を目標にしています。 (1)実際の見聞、専門書や文献等により調査する (2)調査結果を分析し、まとめる (3)調査結果のまとめから、解決すべき課題を設定する (4)課題を解決するための方法を考え、具体的計画を立案する 創造プロジェクトII」では、「創造プロジェクトI」で企画立案したプロジェクトに従って実際に作品を作ることを目標にしています。 (1)自主的に作品づくりをする(自主性を養います) (2)チームで共同して作品づくりをする(協調性を身に付けます) (3)期間内に成果をまとめ、発表する(プレゼンテーション能力を高めます) 「工学リテラシー入門」
 「失敗しつつもそれを強い意欲で乗り越えて成功する体験を組み込んだ」教育プログラム(「やってみせ、させてみて教育」と呼ぶ)を行うため、開設している科目です。
「知識の暗記だけで使えるつもりになっている」“つもり学習”の悪癖に気づき、勉学姿勢を自ら改めることで、工学を使いこなす能力を育成するための基礎となる勉学習慣の形成を目的としています。 「失敗しつつもそれを強い意欲で乗り越えて成功する体験を組み込んだ」教育プログラム(「やってみせ、させてみて教育」と呼ぶ)を行うため、開設している科目です。
「知識の暗記だけで使えるつもりになっている」“つもり学習”の悪癖に気づき、勉学姿勢を自ら改めることで、工学を使いこなす能力を育成するための基礎となる勉学習慣の形成を目的としています。〜「やってみせ、させてみて教育」〜 ◇やってみせること 実施テーマに関連した研究のおもしろさと難しさについて,第一線の技術者・研究者の方々から,話を聞きます。 ◇自分たちでやってみること 第1段階 ・課題と目標をまとめる ・課題遂行に向けたスケジュールを作成する ・構造・材料などを考えて、設計・製作する 第2段階 ・「期待通りの結果が得られない」、この失敗を4年生の先輩を含めて話し合う ・討議の結果を課題達成のための方法に反映させ、再度、設計・製作する 第3段階 ・製作の経緯と達成感をまとめ・発表する |
 |
|
