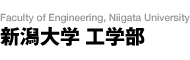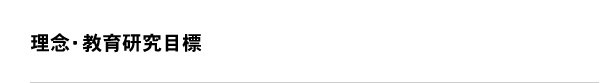新潟大学工学部は、新潟大学の理念を踏まえ、創造力と総合的判断力を有する有為な人材を育成し、基礎から応用にわたる国際的水準の研究を推し進め、社会と連携しつつ、自然との調和に基づいた人類の幸福に工学を通して貢献する。
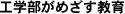 |
ものづくりをたいせつにする心を育む
豊かな創造力と柔軟な思考力を育む
高い自主性と倫理観に支えられた実践力を育む
基礎的な事象を正しく理解し、かつ全体を総合的に判断できる能力を育む
一つの分野だけでなく、学際的ではば広い知識を育む |
 |
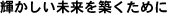 |
資源循環型社会の実現を目指した技術の開発
理性・感性をもつ知的なコンピュータの実現
自然環境との調和を目指した建設技術の開発
地球と生物に優しい恒久的エネルギーの開発
21世紀を支える画期的新素材・新材料の開発
ミクロマクロな視点からみた合理的物質生産
インテリジェント機器が支える心豊かな社会の構築 |

- 教育目標
広い視野、豊かな人間性・国際性、社会に対する高い倫理性を涵養し、大学院と連携しつつ専門分野に対する確固とした基礎学力と応用力を養う。また、体験学習を通して、物作りの楽しさを実感させつつその基礎技術を習得させ、現象の複雑さとその工学的解決方法を理解させる。
- 研究目標
国際的評価を得ることを目標に研究を促進し、既に国際的水準に達している研究についてはそれを更に発展させる。また、本学の特徴である総合性、学際性、地域性のある研究を支援する。さらに、社会貢献ならびに他の研究機関との連携を積極的に行う。

目標達成のため以下の施策を進めるが、自己点検・評価と外部評価を継続的に行い、その結果に基づき改善に努める。
- 教育目標達成のための施策
- 履修科目登録の単位数の上限を設定するとともに、教養科目とコア科目を重視したカリキュラムの改善を行う。
- 低学年では、できるだけ学科の壁にとらわれない基礎的授業を行い、学年進行に伴い専門性を賦与する。一方で、入学初期から専門分野に興味を持たせるための授業科目を設ける。
- 可能な限り少人数クラスとし、レポートや宿題等により学生に自主勉学を促し、教員と学生との信頼に基づいた双方向教育を行う。
- 3.の実効を上げるためTA制度の拡大と活用を図る。
- GPAを導入し、履修科目登録単位数の上限設定と連動させて、履修指導、進級、進路指導等の資料とする。
- シラバスに授業科目の内容・進行計画、評価基準、参考書・資料等を明示し、厳格な審査に基づき単位を認定する。
- 学生を授業改善の協力者にする。即ち、学生は教員の行った講義内容や教授方法等に対して授業評価を行い、教員はこれを授業改善の参考にする。
- インターンシップ、工場・現場見学、社会人による特別講義等により社会における体験と知識を与える。英語による授業・講演会の実施を促進する。資格取得を奨励し、取得のための指導・助言等を行う。
- 卒業研究の発表等を利用してプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力の育成に努める。
- 入試方法・科目の検討と改善を行う。
- 学生の就職・進学指導になお一層の努力をする。
- 海外の大学を含めた教育機関との単位互換を促進する。
- 公開講座、生涯教育、社会人教育に積極的に取り組む。
- 小・中・高校生、社会人向けの大学開放を積極的に行う。
- 上記1.〜14.の施策を達成するため、FDを積極的に行う。また、教職員を対象として教育賞を、学部4年生を対象として卒業研究(設計)に対する優秀賞を表彰する。
- 研究目標達成のための施策
- 各教員に研究の進展を促し、国際会議における発表、権威ある学術雑誌への投稿、国際的プロジェクトへの参加等を奨励する。
- 若手教員の海外留学を奨励し支援する。
- 学内外の研究機関との共同研究を推し進める。学内的には自然科学系他部局との連携はもとより、生命科学系、人文社会科学系との共同研究を促進する。
- 産学官連携を積極的に推進し、地域との連携を深める。
- 東北アジア地域における新潟県の立地性並びに新潟市の拠点性を念頭におい研究を支援する。
- 外国大学との共同研究・学術交流協定締結を推進する。
- 知的所有権の取得を奨励する。
- ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーならびにTLO設置・発展を支援する。
- 科研費獲得及び他の外部資金導入を促進する。
- 教員各自の研究内容を分かり易く公表する。その際、当該研究が世界において占めている位置や社会における意義等とそれに対する自己評価を添える。日本語および英語によるホームページを開設する。