Informatio
3年ぶりにJGR-Atmospheresに論文が受理されました。(2025.03.25)
JPCZの温暖化後の熱力学・力学的な変化に関する研究論文が,JGR-Atmospheresに受理されました。松永直君の卒業論文に中村准教授が解析を加えて論文を投稿しました。同世代の世界トップレベルの北米研究者(査読中に名乗ってきました)の査読意見は極めて建設的でしたが,32ページに及ぶ返答資料の作成は流石に厳しかったです。今後はNature Publishing Groupの論文誌への受理を目指して精進したいと思いますので,末永くどうぞよろしくお願い申し上げます。永井先生の技術講演会(2024.12.9)
我が国の波浪観測情報ネットワーク(NOWPHAS)の開発や,海岸港湾工学分野において海外技術協力を行ってきた永井紀彦先生をお招きして160名を超える聴講者のもと技術講演会を実施しました。永井先生は国家公務員総合職試験を土木工学分野1位で国土交通省に入省された経歴を有しており,我が国を代表する海岸工学者として活躍されてきました。メキシコをハブとした第3国への海岸工学の技術協力では,技術供与を受けた国(メキシコ)も主導的な立場としてイニシアティブを享受できる仕組みがよくできていると思い,大変勉強になるご講演でした。(2024.12.12 posted by R.N.)
第38回International Conference on Coastal Engineering Rome 2024に参加しました。(2024.09.11)
OBの青木、M2の兼村・佐藤、M1の佐々木がローマで開催された国際学会ICCEに参加し、口頭発表を行いました。海岸工学分野における世界中の技術者が集まる学会において,ローマの歴史ある建造物における発表だけではなく,テクニカルツアーや晩餐会において国内外の技術者と親睦を深めることができました。
(2024.10.09 posted by K.S.)
植生が風速下の越波流量を減少させる。(2024.08.12)
植生と風速下の越波流量の関係を調査した研究が,国際学術誌『Ocean Engineering』に投稿からわずか63日で受理されました(Link)。二次元風洞水槽及び植生模型を用いた世界初の水理実験を行い,植生密度が大きくなるほど風速下の越波流量が指数関数的に減少することを明らかにしました。また,風速及び植生の影響を考慮した越波流量予測式を世界で初めて提案しました。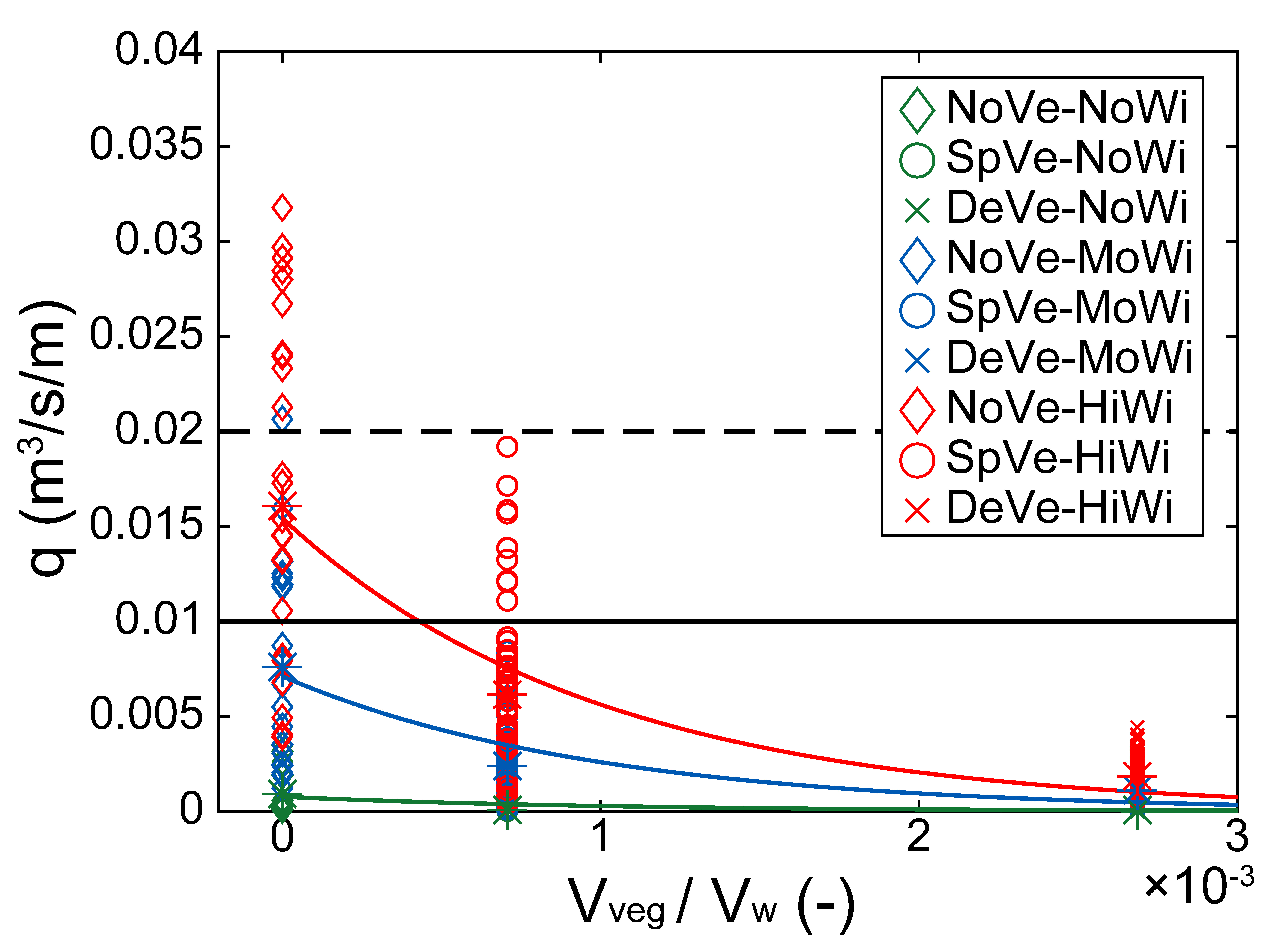
植生体積と越波流量の関係.実線は指数関数による近似曲線. (2024.08.12 posted by Y.A.)
研究室開室5周年を迎えました。(2024.3.24)
研究室開室5周年を迎えました。令和5年度は予測不確実性が高い年度で,公私ともに年度初めには想定できなかったようなとても良い結末を迎えました。また,極めて優秀な学生達によって当研究室も格別の発展を見せたと思います。今後,論文成果の質と量の向上と,新しい研究開発への挑戦を継続したいと思いますので,どうぞよろしくお願い申し上げます。
(2024.3.28 posted by R.N.)
新潟海岸における海浜侵食の研究成果 (2024.01.22)
新潟大学海岸工学研究室が開設当初より行っていた新潟海岸の海浜変形(浜崖)に関する研究が『Estuarine, Coastal and Shelf Science』(Elsevier社)に100日の査読期間で無事に受理されました。現地調査と数値計算モデルを用いた新潟海岸の浜崖に関する研究ですので,もしご興味がありましたらご覧ください(Link)。2023年度は新潟に関する研究イベントが多い年だったように思います。令和5年度日本沿岸域学会全国大会 (2023.7.22-23)
令和5年度日本沿岸域学会全国大会を開催しました.22日には新潟大学工学部で研究討論会を,23日午前は駅南キャンパスときめいとで講演を実施しました.また,23日には新潟港湾空港整備事務所のご厚意で,信濃川下流から新潟海岸まで船上視察しました.御高名な先生方も多数見学されていました.関係者の皆様,ありがとうございました.当研究室は引き続き精進してまいりますので,末永くどうぞよろしくお願い申し上げます。(1) 温暖化後のアフリカ・Volta Riverの浸水強度増加へ言及 (2022.12.06)
当研究室の高山遼太君が卒業研究で行った研究では,気象・水文・河川洪水モデルによる浸水面積の算定値と衛星データの解析値を比較して,大陸河川の浸水面積を予測する手法を構築しました.温暖化後の河川流量と浸水面積の増加を示唆した研究成果は水文学の国際学術誌(Journal of Hydrology: Regional Studies)に受理されました.(2)ICCE Sydney 2022で発表しました. (2022.12.04.~09)
シドニーで開催された海岸工学のプレミア国際学会であるInternational Conferece on Coastal Engineering in Sydney 2022で6件(本研究室学生から4件)の発表を行いました.私も4年ぶりに学会で発表しましたが,相変わらず鋭い質問を受けました.多くの国が海岸を有しているため,国を超えた共通の議論ができます.海外との新しいネットワークも構築できそうですので,今後の展開と2年後のローマでの開催を楽しみにしています.(3)転移学習を用いた有義波高の高精度予測 (2022.10.28)
国際学術誌Ocean Engineeringで発表した論文では,学習済みのデータセットを転移することで,わずか1か月分のデータセットで高精度な有義波高の機械学習を行いました.従来では数年~10数年のデータを必要とする機械学習による波浪予測の限界を部分的に解決したうえに,機械学習による波浪予測の既往研究と同等もしくは高精度な予測結果を算定できました.投稿からわずか3か月で原稿が受理されました.(4)第47回海洋開発シンポジウムでの発表 (2022.7.1.)
学生3名が土木学会論文集に受理された論文(卒業論文で実施した研究内容)に基づいて,海洋開発シンポジウムで発表しました.3名の発表には他大学の先生から多くの質問があり,研究室の学生も的確に返答するように努めていました.今後の研究の参考になる意見も頂くこともできました.質問された先生方,ありがとうございました.これからも学外への研究成果の発信を積極的に行って参ります.来年の対面の学会を楽しみにしています.
(5) 着任して3.5年が経過しました (2022.7.1)
新潟大学に着任してから3.5年が過ぎました.全く何もないところから4人で始まった海岸工学研究室は成長して,国際学会や国際学術誌に論文を投稿したり,建設業系のスタートアップも創れる研究室になりました.優秀かつ向上心の高い学生や,技術職員の石橋様がいらっしゃりと,今なお人財に大変に恵まれています.この調子で研究室とともに成長して参ります.
(6) 南アメリカ大陸の亜熱帯低気圧の温暖化後へ言及 (2021.12.27)
南アメリカ大陸の低気圧は発生頻度が低く,温暖化後の傾向はよく分かっていませんでした.2021年に発表した論文では,2010年亜熱帯低気圧Anitaを温暖化後の物理場上で数値計算することで,世界で初めて南アメリカ大陸亜熱帯低気圧が温暖化後に強度が増加することを明示的に言及しました.受理された権威ある国際学術誌の2021年のIFは5を超えていて,達成感がありました. [ JGR:Atmospheres 126(24): e2021JD035261.
(7) GUIリモート接続環境の構築
コロナウイルスを起因とした社会的情勢の変化によって3密を防ぎながら社会的活動を行う必要に迫られています.これは研究活動も例外ではありません.ここでは,Linux OS (Cent OS7) のパソコンをWindows10からリモートで動かす二つの方法を紹介します. A. Teraterm + Xming を用いるとLinux上のmatlabも遠隔操作可能です.B. Windows搭載のリモートデスクトップを用いるとLinux上のmatlabの遠隔操作はできないようですが,Teratermよりも動作性が良いです. また,MacOSからLinuxやMacOSへのリモート接続,WindowsからWindows (操作される側すなわちホスト側のパソコンはWindows Homeではなく,ProやEnterpriseとする必要があります) へのリモート接続については比較的容易にできますので,それらが紹介されているWebサイトもあります.